古代エジプト史上、最も偉大で有名な王として知られるラムセス2世。
彼の長い治世は、数多くの建築物や戦争の逸話だけでなく、その家族関係、特に妻たちの存在によって彩られています。
この記事では、「ラムセス2世の妻について詳しく知りたい」というあなたの疑問にお答えします。
最も愛された王妃ネフェルタリを中心に、ラムセス2世の結婚政策、多くの子女、そして知られざる人物像に迫ります。
さらに、よく比較されるツタンカーメンとの関係や、オジマンディアスという異名、気になる死因、そして彼のミイラはどこにあるのかといった謎まで、幅広く解説していきます。
- ラムセス2世が最も愛した妻ネフェルタリの人物像
- 数々の有名な逸話や壮大な神殿建設の背景
- ツタンカーメンとの関係性や時代の違い
- ラムセス2世の死因やミイラの現在の所在地
ラムセス2世の妻|最も愛された王妃ネフェルタリ
- ラムセス2世が迎えた多くの妻たち
- 100人を超えたとされるラムセス2世の子女
- ネフェルタリへの愛を示す有名な逸話
- 妻のために捧げられたアブ・シンベル神殿
- 偉大なる王ラムセス2世の人物像
ラムセス2世が迎えた多くの妻たち

ラムセス2世が迎えた多くの妻たち
ラムセス2世は、古代エジプトのファラオの中でも特に多くの妻を持ったことで知られています。
記録によれば、「偉大なる王の妻」という公式な称号を持つ正妃だけでも8人以上おり、その他にも多数の側室が後宮にいたとされています。
彼の結婚は、単なる個人的な関係にとどまらず、極めて戦略的な意味合いを持っていました。
ラムセス2世の結婚の目的
- 外交・同盟関係の構築:周辺国の王女を妻に迎えることで、国家間の友好関係を築き、平和を維持しました。特にヒッタイトとの和平条約後に、その王女を妃として迎えたことは有名です。
- 王室の血統維持:多くの子供をもうけることで、王家の血筋を確実に後世へとつなぎ、王朝の安定を図りました。
- 王権の正当性補強:有力な貴族の娘や、時には自身の娘や姉妹を妻とすることで、国内の権力基盤を固め、王権の神聖性や正当性を高める狙いがありました。
このように、ラムセス2世の婚姻関係は、古代エジプトという大国の舵取りを行うための高度な政治戦略の一部だったのです。
中でも、第一正妃であったネフェルタリと、それに次ぐ有力な正妃であったイシスネフェルトは、宮廷内で特に重要な役割を果たしました。
100人を超えたとされるラムセス2世の子女

100人を超えたとされるラムセス2世の子女
多くの妻を迎えたラムセス2世は、その結果として非常に多くの子宝に恵まれました。
碑文などの記録から、王子と王女を合わせると、その総数は100人を超えていたと推定されています。
これは古代エジプト王家において前例のない規模であり、ラムセス2世の治世がいかに長く、そして豊かであったかを物語っています。
これらの子供たちは、ただ王家に生まれたというだけでなく、それぞれが国家の運営において重要な役割を担いました。
| 主な役割 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 王子たち | 軍事・行政・神官の要職 | 軍の司令官、主要な神殿の大神官、行政の長官などに任命され、広大なエジプトの統治を支えました。後にファラオとなるメルエンプタハも彼の息子です。 |
| 王女たち | 宗教儀礼・外交(婚姻) | 「神の妻」といった高い宗教的地位に就いたり、父であるラムセス2世自身の妃となったりすることで、王権の神聖性を高めました。また、同盟国の王族に嫁ぐこともありました。 |
特に有名な子女としては、ネフェルタリの死後に正妃となった娘のメリトアメンや、同じく正妃となったイシスネフェルトの娘ビントアナトが挙げられます。
彼女たちは、単なる王女ではなく、父である王を支える重要なパートナーとして、政治や宗教儀式で大きな影響力を持っていたのです。
ネフェルタリへの愛を示す有名な逸話

ネフェルタリへの愛を示す有名な逸話
数多くの妻や子供がいたラムセス2世ですが、その中でも第一正妃ネフェルタリへの愛情は格別だったと伝えられています。
彼女はラムセス2世が王位に就く前からの妻であり、二人の関係は多くのロマンチックな逸話として残されています。
ネフェルタリという名前は「美しき者、比類なき者」を意味し、その名の通り、彼女は類まれな美貌と知性を兼ね備えていたと言われています。
ラムセス2世は、公的な碑文の中で彼女を「我が愛する者」や「太陽がそのために輝く者」といった詩的な言葉で繰り返し称賛しており、これは他の王妃には見られない特別な扱いです。
通常、ファラオの建築物には王自身の功績が刻まれるのが常ですが、ラムセス2世はネフェルタリの美しさや自身の愛情を公然と記録に残しました。
これは、彼らの関係が単なる政略結婚ではなく、深い愛情に基づいていたことを強く示唆していますね。
また、ネフェルタリは政治や外交の場にもラムセス2世と共に姿を現し、王の重要な相談役でもあったと考えられています。
彼女が読み書きのできる高い教育を受けていたことも、その影響力の大きさを裏付けています。
しかし、彼女はラムセス2世の治世25年目頃に亡くなったとみられ、その死は王に大きな悲しみをもたらしたことでしょう。
妻のために捧げられたアブ・シンベル神殿

※イメージです
ラムセス2世のネフェルタリへの愛を最も象徴しているのが、ヌビアの地に建設された壮大なアブ・シンベル神殿です。
この遺跡は、ラムセス2世自身を祀る大神殿と、その隣に建てられた小神殿の二つで構成されています。
驚くべきことに、この小神殿は、妻であるネフェルタリと、愛と美の女神ハトホルに捧げられたものなのです。
古代エジプトにおいて、ファラオが自分のためではなく、王妃のために神殿を建てるというのは極めて異例のことでした。
大神殿と小神殿
大神殿の正面には、高さ約20メートルにも及ぶ巨大なラムセス2世の坐像が4体並んでおり、ファラオの絶大な権力を示しています。
一方で、小神殿の正面には、ラムセス2世とネフェルタリの立像がほぼ同じ大きさで交互に並べられています。
これは、王が王妃を自分と対等に近い存在として扱っていたことの証と言えるでしょう。
小神殿の入り口には、「偉大なる王ラムセス2世は、その最愛の妻、ネフェルタリのためにこの神殿を造った」という趣旨の碑文が刻まれています。
王が自身の建築物に、妻への愛をこれほど明確に記した例は他にありません。
このアブ・シンベル神殿の存在は、ネフェルタリがラムセス2世にとって単なる妻の一人ではなく、宗教的にも政治的にも不可欠なパートナーであったことを、後世に雄弁に物語っています。
偉大なる王ラムセス2世の人物像
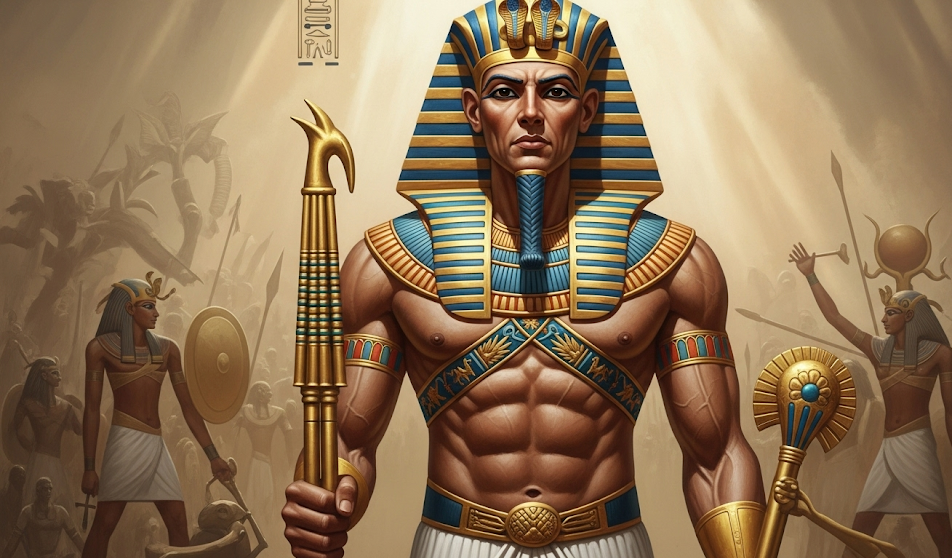
偉大なる王ラムセス2世の人物像
ラムセス2世は、妻や家族を深く愛する一面を持つ一方で、古代エジプト史上最も強力な指導者の一人でした。
彼の治世は約66年にも及び、その間にエジプトは空前の繁栄を遂げます。
彼の人物像を語る上で欠かせないのが、軍事指導者としての側面です。
特に有名なのが、即位後まもなく起こったヒッタイト帝国との「カデシュの戦い」です。
この戦いでラムセス2世は、自ら戦車を駆って敵陣に突入するなど、獅子奮迅の活躍を見せたと伝えられています。
戦いの結果自体は引き分けに近かったものの、ラムセス2世はこれを大勝利として国内に喧伝し、自身の英雄的なイメージを確立しました。
また、彼は優れた外交官でもありました。
長年の宿敵であったヒッタイトとの間で、世界史上初とされる平和条約を結んだことは、彼の大きな功績の一つです。
この条約により、両国間の安定がもたらされ、エジプトはさらなる繁栄の時代を迎えることになります。
建築家としても類まれな才能を発揮し、前述のアブ・シンベル神殿をはじめ、ラメセウム(葬祭殿)や新都ペル・ラムセスなど、エジプト各地に数多くの壮大な建造物を残しました。
これらの活動を通じて、彼は自身を神格化し、ファラオの権威を絶対的なものへと高めていったのです。
ラムセス2世の妻以外の功績と死後の謎
- ツタンカーメンとの時代的な違いとは
- オジマンディアスという名の由来と意味
- ラムセス2世の死因は自然死だったのか
- ラムセス2世のミイラはどこにある?
ツタンカーメンとの時代的な違いとは

ツタンカーメンとの時代的な違いとは
古代エジプトのファラオとして、ラムセス2世としばしば比較されるのがツタンカーメンです。
しかし、この二人の間には直接的な血縁関係はなく、活躍した時代も大きく異なります。
ツタンカーメンは、ラムセス2世より約100年前に在位した第18王朝のファラオです。
彼の父アクエンアテンが行った急進的な宗教改革の混乱を収拾し、伝統的なアメン神信仰を復活させたことで知られています。
しかし、彼は10代という若さで亡くなり、その治世は約9年と短いものでした。
一方、ラムセス2世は、その後の第19王朝のファラオです。
彼は、第18王朝末期の混乱から国を立て直し、エジプトを再び強大な帝国へと押し上げました。
つまり、ツタンカーメンが「混乱からの回復期」の王であったのに対し、ラムセス2世は「帝国の絶頂期」を築いた王と言えます。
| 項目 | ツタンカーメン | ラムセス2世 |
|---|---|---|
| 王朝 | 第18王朝 | 第19王朝 |
| 在位期間 | 約9年 | 約66年 |
| 主な功績 | 伝統宗教の復活 | 領土拡大、神殿建設、平和条約締結 |
| 時代の特徴 | 宗教改革後の回復・安定期 | 新王国時代の最盛期・絶頂期 |
このように、二人はエジプト史における異なるフェーズを象徴する存在であり、その治世の長さや残した功績の規模には大きな違いがあるのです。
オジマンディアスという名の由来と意味

オジマンディアスという名の由来と意味
ラムセス2世は、後世、特に西洋世界において「オジマンディアス(Ozymandias)」という名前でも知られています。
この名前は、ラムセス2世の即位名である「ウセルマアトラー」が古代ギリシャ語に伝わる過程で変化したものと考えられています。
この名前が世界的に有名になったのは、19世紀のイギリスの詩人パーシー・ビッシュ・シェリーが書いた『オジマンディアス』という詩がきっかけでした。
この詩は、砂漠で発見された巨大な王の像の残骸を描写しています。
像の台座には、「我が名はオジマンディアス、王の中の王。我が功績を見よ、そして絶望せよ!」という傲慢な言葉が刻まれているにもかかわらず、その周りには何もなく、ただ果てしない砂漠が広がっているだけです。
シェリーの詩によって、「オジマンディアス」という名前は、「どれほど絶大な権力を誇った者も、時が経てばその栄華は失われ、やがて忘れ去られてしまう」という、権力の無常さや儚さの象徴として広く認識されるようになりました。
もちろん、ラムセス2世自身がそのような意図で自らを称していたわけではありません。
彼は自身の功績が永遠に語り継がれると信じて、数多くの巨大な建造物を残しました。
しかし、皮肉にも、その異名であるオジマンディアスは、栄光の裏にある物悲しさを私たちに伝えているのです。
ラムセス2世の死因は自然死だったのか

ラムセス2世の死因は自然死だったのか
約66年という驚異的な長さの治世を全うしたラムセス2世ですが、その最期はどのようなものだったのでしょうか。
彼のミイラに対する現代の科学的な調査から、その死因について多くのことが明らかになっています。
結論から言うと、ラムセス2世の死因は、特定の病気や事件によるものではなく、高齢による自然死であった可能性が最も高いと考えられています。
彼のミイラをCTスキャンで調査した結果、死亡時の年齢はおよそ90歳であったと推定されました。これは、古代エジプト人の平均寿命をはるかに超える長寿です。
ミイラからは、長年の人生を物語るいくつかの病気の痕跡が見つかっています。
- 重度の関節炎:背骨や関節に深刻な関節炎の痕跡があり、晩年はかなりの痛みに悩まされていた可能性があります。
- 歯の問題:歯がひどく摩耗しており、歯周病や歯根の膿瘍も見つかっています。これもまた、激しい痛みを引き起こしたと考えられます。
- 動脈硬化:血管の状態から、動脈硬化が進行していたことも分かっています。
一部で噂されるような、戦死や暗殺といった説を裏付けるような外傷の痕跡は、ミイラからは一切発見されていません。
彼は多くの病を抱えながらも、天寿を全うしたというのが、現在の科学的な見解です。
ラムセス2世のミイラはどこにある?

ラムセス2世のミイラはどこにある?
古代の偉大な王のミイラが、今もなお現存しているという事実は、多くの人々の好奇心をかき立てます。
「ラムセス2世のミイラはどこで見られるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
ラムセス2世のミイラは、1881年にエジプトの「王家の谷」近郊にある、ミイラの隠し場所(DB320)で他の多くの王たちのミイラと共に発見されました。
古代の墓泥棒からミイラを守るため、新王国時代の神官たちが一か所に集めて隠していたと考えられています。
現在の所在地
発見されたラムセス2世のミイラは、現在、エジプトの首都カイロにある「エジプト国立文明博物館(NMEC)」に安置・展示されています。
以前はカイロ中心部のエジプト考古学博物館にありましたが、2021年に行われた「ファラオの黄金のパレード」と呼ばれる壮大な移送イベントを経て、より新しい設備の整った現在の博物館に移されました。
エジプト国立文明博物館では、温度や湿度が厳密に管理された特別な展示室で、ラムセス2世の安らかな寝顔を間近に見ることができます。
3000年以上もの時を超えて保存されてきた偉大なファラオの姿は、訪れる人々に深い感動と歴史の重みを感じさせてくれます。
まとめ:ラムセス2世と妻が紡いだ歴史
- ラムセス2世は古代エジプト第19王朝の最も偉大なファラオの一人
- 彼の治世は約66年間に及びエジプトに空前の繁栄をもたらした
- 外交や血統維持のため8人以上の正妃と多くの側室を妻に迎えた
- 最も有名な妻は第一正妃のネフェルタリで深い愛情で結ばれていた
- ネフェルタリの名前は「美しき者、比類なき者」を意味する
- 妻ネフェルタリのためにアブ・シンベルに小神殿を建立したのは異例
- 生涯で100人を超える王子や王女をもうけたとされる
- 子供たちは軍事や宗教など国家の要職を担い王権を支えた
- カデシュの戦いでの武勇伝など数多くの逸話が残されている
- 世界最古とされる平和条約を宿敵ヒッタイトと締結した
- ツタンカーメンとは時代も王朝も異なり直接的な関係はない
- ギリシャ語名のオジマンディアスは権力の無常の象徴として知られる
- 死因は90歳前後での老衰による自然死が最も有力視されている
- ミイラはカイロのエジプト国立文明博物館に所蔵され見学可能
- ラムセス2世と妻たちの物語は今なお多くの人々を魅了し続けている
